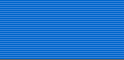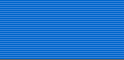|
Q1.
|
当校では、卒業式や入学式で卒業生名一覧や入学者名一覧、また、式での座席(名前入り)などの配布を式に列席される方全員に行っておりますが、4月以降は、配布にあたって名前を記載している学生全員の同意が必要となってくるのでしょうか?
また、学生全員の同意が得られるか否かに関わらず、式の終了後に回収する必要も出てくるのでしょうか?
|
|
A1.
|
生徒にとって、卒業式や入学式で自らの氏名が入った名前一覧が配布されることは、入学する意思、卒業する意思がある者であれば、納得していることではないかと考えられます。
そのため、同意をすべからく生徒全員から取る必要はないと思われますし、現実的でないと思われます。
|
|
Q2.
|
学校案内や募集パンフレット、新聞等に在学生や卒業生の氏名、コメント、写真、出身校等を掲載する場合について合意は必要ですか。また留意点は何ですか。
|
|
A2.
|
個人情報保護法でも第三者提供に当たりますが、それと同時にプライバシーの権利も考慮する必要がありますので、そうした観点からも、生徒の同意を取る必要はあるでしょう。個人情報保護法上でも、この場合であれば、生徒に個人情報保護法で規定されている「同意」を取ることが必要だと思われます。
|
|
Q3.
|
広報活動の一環として、就職決定者の名前・写真・就職先(会社名と住所の一部)をチラシに掲載してきましたが、この場合、本人と就職先の了解を得なければならないのでしょうか。
|
|
A3.
|
本人に関しては、Q2と同様の回答となります。また、就職先の了解についてですが、個人情報保護法で対象とされる個人情報は、生存する個人の情報です。そのため、就職先の了解は必要ないと思われます。
|
|
Q4.
|
学籍簿や学校日誌等、個人情報に関する保管書類は今後どう扱っていけば良いのでしょうか。
|
|
A4.
|
個人情報保護法における安全管理措置に関する扱いが必要です。
|
|
Q5.
|
個人情報の保管にあたり、重要度により段階を区別して扱う方法で妥当ですか。
|
|
A5.
|
個人情報を保管するに当たり、重要なものとそうでないものとの区別はありません。そのため、個人情報であれば同じように扱う必要があります。
|
|
Q6.
|
個人情報の同意が有効な期間はありますか。例えば、入学時に一度、同意を求めれば良いのでしょうか。情報の内容が異なればその都度同意を求めるのでしょうか。
|
|
A6.
|
個人情報の同意について、有効な期間という概念はありません。なお、入学時に、使用目的を明らかにしておけば、いくつかのものについて同時に同意を取るといったやり方はあります。
|
|
Q7.
|
試験等の成績や順位表等を校内に掲示することはやめるべきでしょうか。学生番号と点数のみの掲示でも問題がありますか。また、推薦入学者の入学後の成績を(よりよい学生の推薦を期待する意味で必要と考え)開示請求とは関係なく、高校長(推薦者)に該当学生の同意を得て通知していますが、問題ないですか。
|
|
A7.
|
前者の場合には、いわゆるオプトアウトの方式をとればよいのではないでしょうか?学内の方針で生徒の学習上の成果を示す必要があるので試験等の成績等を公表するが、申し出等があった場合には、そうした方法を行わないこととする、としておけばよいと思われます。なお、後者の場合は問題はないと思われます。
|
|
Q8.
|
入学選抜試験等は開示しなくてもよいとありますが、その場合、その旨を学内向けに発表すればよいのでしょうか、それとも学校の募集要項に明記するなどして、外部に向けて発表すべきでしょうか。
|
|
A8.
|
入学選抜試験については、昨今結果等を開示するところも出てきていますが、学校の判断において、受験生等に開示すべきかどうかを決める必要があります。学内における検討の結果、開示しないという整理であれば、開示請求があった場合、「当校において試験結果を開示することは、○○の理由からふさわしくないと考えるため、開示いたしません」と理由を提示した上で、相手にお示しすることが必要でしょう。
|
|
Q9.
|
第三者から指摘を受け訴えられた場合、法的措置がどの程度まで有り得るものですか。法令に違反した場合どのようなことが想定されますか。
|
|
A9.
|
個人情報の利用状況について問われた場合の個人情報が漏洩した場合の2点が想定されます。特に、法的措置が問題となるのは後者です。中には、1人あたりの個人情報の漏洩で1万円の損害賠償が生じた例もありますので、個人情報の漏洩については、心して対応する必要があります。なお、第三者提供の場合には、当該本人から求めがあった場合には、直ちに情報の提供を停止することが求められます。
|
|
Q10.
|
入学時または入学前ガイダンス時に今後の学校生活における個人情報(氏名・住所・成績等)に関して、全てに該当させるような表記を(例示を含めて)することにより、目的と同意を包括的にとることに問題が発生しますか。また、同時に卒業アルバムや同窓会名簿への利用について同意を求めた場合、その利用目的の範囲が曖昧になり適切でない印象を与えないでしょうか。
|
|
A10.
|
個人情報は、それを渡す個人にとって何に利用されるのかが明確であるようにしておく必要があります。そのため、抽象的な文言の利用目的では不十分です。あくまで、利用目的は個人情報を渡す個人が分かる程度に明確にすることが大切です。なお、卒業アルバムや同窓会名簿作成のため、という程度の特定であれば、利用目的が特定されているといえるのではないかと思われます。
|
|
Q11.
|
クラス連絡網等、一部の保護者、学生が記載を嫌がる場合、全員配布はできないのでしょうか。また、卒業アルバムの住所録に一人だけ同意が得られなかった場合や、卒業時に同窓会名簿の作成反対者が出た場合はどうすればよいですか。
|
|
A11.
|
まず、ここにあがっている例(クラス連絡網、卒業アルバム)にある住所等の情報は、生徒に渡す場合でも第三者提供となります。この場合、同意が得られない場合、少なくともその者だけは名簿等に載せることは難しくなってくるでしょう。
|
|
Q12.
|
クラス担任は、常にクラスの学生の住所等の個人情報を持たなければならないが、これは各校の判断に任せられるのでしょうか。
|
|
A12.
|
この場合、クラス担任は、学校が生徒の住所等を入手する際に、利用目的を示して入手した個人情報を持っているという整理になりますから、クラス担任が生徒の個人情報を持つことは問題ありません。
|
|
Q13.
|
書類(財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書、監査報告書)の開示をする場合、明細まで全てを開示するのですか、ダイジェスト版でもよいのか?
|
|
A13.
|
あくまで私立学校法上の問題であると思われますが、明細までは開示することは求められていないと思われます。
|
|
Q14.
|
個人情報の場合は本人以外に閲覧拒否することは可能ですか。
|
|
A14.
|
生徒が未成年であるかという点が問題となってくるものと考えられます。生徒が未成年であれば、親等が保護者の立場で閲覧することは防げないのと考えられます。
|
|
Q15.
|
開示場所は学内から離れた場所でも良いのですか。
|
|
A15.
|
生徒の利便性を考えるであれば、学内が原則であり、そうでない場合でも近い場所であることが求められます。
|
|
Q16.
|
開示請求者の本人確認の権利は学校側にありますか。その手段はどの程度まで求めてよいのですか。また、開示拒否の対処はどうすべきですか。拒否理由を告げる必要がありますか。
|
|
A16.
|
本人確認については、学校側が行うべきであり、その権利もあるものと思われます。別人が悪意で開示請求を行ってくることも想定できないわけではありません。学校としては、身分を証明するものを提示することが、開示請求の際に必要である旨、提示してよいのではと思います。
また、開示拒否については、理由を付した上で相手に回答することが求められると思われます。そのため、どのようなものが非開示とするか、理由を考えた上で前もって定めておくことがよいのではないでしょうか。
|
|
Q17.
|
閲覧時期については即時ですか、それとも請求後何日以内といったように期限がありますか。
|
|
A17.
|
このような期限はありません。基本的に個人情報は開示請求があった場合に、すぐに対応できるように体制を整えてことが望ましいといえるでしょう。
|
|
Q18.
|
閲覧の際、転記やコピーを許可しますか。
|
|
A18.
|
個人情報の開示の際のマニュアルを定める際に、たとえば、転記やコピーを認めないという方法はありえると考えられます。一般的に考えても、無条件で(たとえば黒塗りなどをせず)コピーさせるのは、個人情報の漏洩となる恐れがありますから、適切ではないでしょう。
|
|
Q19.
|
閲覧対象者の法人との雇用契約とは非常勤講師を含みますか。
|
|
A19.
|
個人情報保護法は、「個人情報取扱事業者」の単位で個人情報保護のための整備を行うことを予定しています。そのため、学校法人であれば、法人に勤務する者が「個人情報取扱事業者」の枠内に入ってきます。そのため、非常勤講師など常勤でなくとも、学校法人に勤務している者であれば、正規職員と同様になります。
|
|
Q20.
|
学生その他へのDMを業者へ委託し発送する場合も、個人情報の提供と解釈されるのでしょうか。また、同一の学校法人に二つの学校を有し、異なる教育課程を実施している場合、当該個人にパンフ等を送付するための法人内での情報共有は可能ですか。
|
|
A20.
|
事務の委託として業者にDMの送付を依頼する際、業者の側でただ単にDMの配布のために、住所等の情報を利用するということであれば利用目的の変更や第三者への提供とはなりません。
しかし、業者の側で、情報を集めてリストを作り、そのリストを基に勧誘をするといった行為をするのであれば、この場合は、利用目的の変更として本人の同意が必要であるということになってきます。
|
|
Q21.
|
国と学校(法人)間には地方自治体が介在しているが、自治体間の連携や情報共有は実現されているのでしょうか。(隣接県でも内容・水準・対応に格差を感じることがある。)
|
|
A21.
|
各自治体で個人情報保護のための条例等を作成している例があると思われます。そのため、自治体ごとに異なった個人情報保護のための体制をとっていることは想定されます。そのため、何県かにまたがって学校を設置しているところなど、各自治体の体制を確認することが必要です。
|